※約2時間の公演となります(休憩20分あり)。
※やむを得ない理由で出演者や曲目等が変更となる場合や、公演が中止となる場合がございます。公演中止の場合をのぞき、チケット代金の払い戻しはいたしません。
ABOUT THIS CONCERT特徴
2025年11月Aプログラム 聴きどころ
本日のプログラムは、指揮者シャルル・デュトワが最も得意とするレパートリーの中から、メシアンの《神の現存の3つの小典礼》と、ホルストの《組曲「惑星」》という大曲の二本立て。ほぼ30年の時を経て生まれたこの2つの20世紀作品には、共通点よりもむしろ補完的な特徴が多く見られる。メシアンの宗教色、そして弦楽器中心の編成、神秘的な音色のオンド・マルトノやピアノのソロ。ホルストは占星術からの影響、木管・金管・打楽器の活躍が目立つ。なお、どちらにも女声合唱があるが、メシアンの場合は主役として扱われ、ホルストでは一部分に脇役として登場するに過ぎない。人間の古くからの大きな関心事である宗教や天体が、20世紀の作曲家と出会い、異なる2つの素晴らしい管弦楽曲に成就した。
(野平一郎)
PROGRAM曲目
メシアン/神の現存の3つの小典礼*
20世紀の大作曲家で宗教の影響を最も色濃く受けた創作をおこなった作曲家と言えば、まずオリヴィエ・メシアン(1908〜1992)の名が思い浮かぶ。敬虔(けいけん)なカトリック信者だった彼は、その大部分の作品で聖書を素材にしている。ドビュッシーやラヴェルの世代のフランス音楽、またストラヴィンスキーなど世紀初頭のさまざまな作品に影響を受けつつ、1940年代になってからメシアンは、ヨハネの黙示録に基づく《世の終わりのための四重奏曲》、神秘主義的な題材に基づく2台ピアノのための《アーメンの幻影》や、ピアノ・ソロのための《みどりごイエスにそそぐ二十のまなざし》といった大作を矢継ぎ早に生み出し、その創作力の高まりの上にこの作品は書かれた。編成はピアノとオンド・マルトノのソロ、弦楽合奏と打楽器、女声合唱である。メシアンの創作におけるピアノの重用は、弟子のひとりでありのちに結婚したイヴォンヌ・ロリオの存在が大きい。また、この作品はピアノ以外にもオンド・マルトノ、チェレスタなどの鍵盤楽器、ヴィブラフォーンなどの鍵盤打楽器などが使われ、バリのガムランを模したメシアンの独特な管弦楽法の先駆けとなった。
すでに1931年から彼はパリのサン・トリニテ教会のオルガニストを務めていたが、その前衛的な響きによる即興演奏は、保守的なカトリック教会の会衆内でしばしば物議を醸していた。メシアンは『わが音楽語法』という著書に自らの音楽語法をまとめ上げ、使用する独自の旋法やリズムの取り扱いを詳しく述べていたが、この作品はそこに書かれている「移調の限られた旋法」が使われている。旋律とバスとがユニゾンで動くメシアン独特の和声、そしてそれが複数重なった時にもたらされる極彩色。また第2楽章などで現れる付加価値を伴うリズムが、既存の音価よりさらに短いそれを挿入し、不安定で興味深い持続を作品に与えている。通常は保守的な典礼の音楽に対して、この作品の新しい音響感覚、そして信仰告白のようなメシアン自身のテクストを巡って、初演は大変なスキャンダルの的となった。
第1楽章〈内的「会話」のアンティフォナ〉、第2楽章〈「言葉(ヴェルブ)」のセクエンツィア、神の賛歌〉、第3楽章〈愛による「遍在」のプサモルディア〉と題され、作曲者によれば、各々神の別の存在を表現しているという。
(野平一郎)
演奏時間:約37分
作曲年代:1943〜1944年
初演:1945年4月21日、ロジェ・デゾミエール指揮、イヴォンヌ・ロリオのピアノ独奏、ジネット・マルトノのオンド・マルトノ独奏、イヴォンヌ・グヴェルネ合唱団、パリ音楽院管弦楽団、パリ音楽院ホール
ホルスト/組曲「惑星」作品32
イギリスの作曲家、グスターヴ・ホルスト(1874〜1934)の代表作で、1914〜1916年の作品。7つの楽章からなる組曲で、太陽系の8つの惑星の中で、地球を除いた7つが扱われている。これはホルストが当時占星学を、またそれとローマ神話との関連について詳しく研究し、構想したことによっている。いずれにせよ、この《惑星》が作曲されるまでに、これだけ体系的に天体をテーマに想像力を働かせた作品はなかったように思われる。ホルストが各惑星に持ったアイデアが多様な音楽的発想と主題系を生み出し、それがオーケストラの扱いに秀でていたホルストの想像力を、この点でさらに刺激したのではなかろうか。特にさまざまな楽器群の特徴を捉えた優れた楽器法の起源は、ワーグナーやリヒャルト・シュトラウスに求められる。多くのイギリスの作曲家と同じく、ホルストもまた彼らの音楽を偏愛していた。しかしイギリスでは20世紀の初頭にナショナリズムとしての民謡の復興運動が起こり、彼はこの運動にも多大な関心を寄せていた。このことは、この作品のいくつかの主題の親しみやすさにも大いに影響を与えている。そしてデュカスやラヴェル、さらにストラヴィンスキーをはじめとする同時代の大陸の音楽を知るようになって、次第に過去の影響から抜け出し、個性的で彼独自のスタイルを確立する。この《惑星》にもその萌芽(ほうが)が見られる。
第1曲〈戦争の神、火星〉、第2曲〈平和の神、金星〉、第3曲〈翼を持った使いの神、水星〉、第4曲〈快楽の神、木星〉、第5曲〈老年の神、土星〉、第6曲〈魔術の神、天王星〉、第7曲〈神秘の神、海王星〉から成る。ただしホルスト自身は「標題音楽ではない」とし、副タイトルは広い意味で解釈してほしいと釘(くぎ)を刺している。実際のところ、全体は純粋な管弦楽組曲として書かれており、7曲の中には多くの魅力的な主題が連続して現れる楽曲もあるが、古典音楽における展開技法に学んだホルストなりの堅固な形式構成が各々に生かされている。全体を見ると、緩徐楽章にあたる第2・5曲と、スケルツォ風の第3・6曲が、組曲中最も著名な第4曲〈木星〉を中心にシンメトリーに配置されている。さらに、5拍子の勇壮でエネルギッシュな第1曲〈火星〉と瞑想(めいそう)的で神秘的な第7曲〈海王星〉と、特徴が最も際立って対照的な2つの楽章が、以上の5曲を取り囲む構成となっている。
最後の第7曲には、女声合唱が歌詞を持たないヴォカリーズで(聴衆に見えないように、という指示がある)加わっている。大管弦楽に合唱のヴォカリーズが一部加わることは1899年に完成したドビュッシー《夜想曲》の〈海の精〉や、1912年に初演されたラヴェルのバレエ音楽《ダフニスとクロエ》の中間部分(間奏曲、ただし混声四部)などに前例があり、こうしたアイデアには当時のフランス音楽の影響があるかもしれない。なお、第4曲の中間部に現れる主題(言わば全体の中心に位置する)は、のちにイングランド国教会の聖歌となった。
(野平一郎)
演奏時間:約54分
作曲年代:1914〜1916年
初演:[非公式初演]1918年9月29日、エードリアン・ボールト指揮、ニュー・クィーンズ・ホール管弦楽団、ロンドン [公式初演]1920年11月15日、アルバート・コーツ指揮、ロンドン交響楽団、ロンドン
ARTISTS出演者
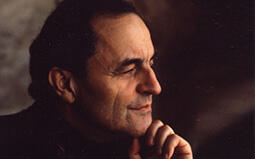 指揮シャルル・デュトワ
指揮シャルル・デュトワ
1936年ローザンヌ生まれ、ローザンヌ音楽院やジュネーヴ音楽院で勉強し、またアンセルメ指揮スイス・ロマンド管弦楽団のリハーサルを見学して指揮の実際について学ぶ。各地の楽団や歌劇場での活動で頭角を現したあと、1977年にモントリオール交響楽団の音楽監督に就任、瞬く間に同団の演奏レベルを引き上げて世界的なオーケストラに育て上げ、2002年までこのポストを務め上げた。一方で1991年から10年間にわたってフランス国立管弦楽団の音楽監督を兼任、その後もフィラデルフィア管弦楽団やロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者などを歴任した。
N響には1987年9月に初登場し、その後数回の共演を経て1996年に常任指揮者に就任、1998年からは音楽監督として同団の発展に努め、2003年に名誉音楽監督となって以降も定期的に客演を行なった。多彩かつ澄明な響きと精緻な造形を追求する彼の音楽作りが、N響の音色のパレットを豊かにし、N響に洗練美をもたらした功績は大きい。
2017年12月の定期のあと、しばらく共演が途絶えたが、昨年NHK音楽祭で久々にN響を振って名演を聴かせた。8年ぶりの定期公演登場となる今回はメシアン、ホルスト、ラヴェルといった彼の真価が存分に発揮されるような曲目が並ぶ。演奏時点で89歳を迎えているデュトワだが、彼らしい精度の高い明晰(めいせき)な指揮で健在ぶりを披露してくれることだろう。
[寺西基之/音楽評論家]
 ピアノ小菅 優*
ピアノ小菅 優*
ドイツを拠点とした少女時代に始まり、小菅優が国際的な活躍を間断なく続けて四半世紀を超える歳月がめぐった。古典派、ロマン派から同時代作品まで旺盛に取り組み、詩的なアイデアと挑戦の意欲を拡げつつ、創造的なプロジェクトを多彩に展開するピアニストである。ピアノ・ソナタ全集に留まらずベートーヴェンの諸作に網羅的に取り組むほか、「水・火・風・大地」の四元素でプログラムを織りなした「Four Elements」、さらには「ソナタ」をテーマとするシリーズ、西村朗や藤倉大とのコラボレーションでも注目されてきた。室内楽や歌曲の演奏にも意欲的な姿勢を保ち、ピアニストとしてだけでなく幅広い音楽家としての探求をさまざまに結実させている。
2022年5月定期公演ではルイージの指揮でラヴェルの協奏曲を聴かせたが、このたびはデュトワが21年ぶりにN響と採り上げるメシアンの難大曲に挑戦。第2次世界大戦中に書かれ、初演から論争を巻き起こした野心作だが、《時の終わりの四重奏曲》をはじめメシアンの音楽に深い関心をみせてきた小菅の確かな知力と表現技量が熱く示されることだろう。
[青澤隆明/音楽評論家]
 オンド・マルトノ大矢素子*
オンド・マルトノ大矢素子*
英国生まれ。東京藝術大学楽理科在学中にオンド・マルトノの音響に魅了され、日本におけるこの楽器の第一人者、原田節(たかし)に師事。以来、演奏・研究の両面からオンド・マルトノにアプローチする。2004年、楽器の開発者モーリス・マルトノ著『アクティヴ・リラクゼーション』を翻訳出版。2006年からパリ国立高等音楽院オンド・マルトノ科で学び、2009年に首席で卒業した。同音楽院在学中、メシアン《神の現存の3つの小典礼》のソリストとしてパリ国立高等音楽院オーケストラとの世界ツアーに参加。帰国後、マルトノの思想研究により東京藝術大学で博士号を取得した。
2011年東京オペラシティ「B→C」シリーズ、2012年NHK-FM「リサイタル・ノヴァ」、2014年NHK-Eテレ「スコラ 坂本龍一 音楽の学校─電子音楽編」などに出演。2017年、メシアンの歌劇《アッシジの聖フランチェスコ》全曲日本初演では第2オンド・マルトノを担当した(シルヴァン・カンブルラン指揮、読売日本交響楽団)。N響とは、2018年8月の「N響ほっとコンサート」以来の共演となる。今回は、デュトワのタクトのもと、メシアンが愛好した独特の浮遊感のある響きを印象深く聴かせてくれるだろう。
[柴辻純子/音楽評論家]
 女声合唱東京オペラシンガーズ
女声合唱東京オペラシンガーズ
東京オペラシンガーズは、故小澤征爾による「世界水準の合唱を」という要請で組織され、以来33年、東京を中心に着実に活動を続けている若手から中堅の声楽家による合唱団。結成直後から「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」(現セイジ・オザワ松本フェスティバル)で活動し、小澤およびサイモン・ラトル指揮のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、リッカルド・ムーティ指揮のシカゴ交響楽団をはじめ演奏史の記憶に残る海外著名オーケストラや歌劇場の来日公演で共演。声質、声量ともに充実した合唱で魅了してきた。2005年より「東京・春・音楽祭」への参加を続けており、2025年は《パルシファル》《蝶々夫人》《こうもり》《ミサ・ソレムニス》などに出演。9月にはムーティ指揮ヴェルディ《シモン・ボッカネグラ》に登場した。N響とは定期公演や「東京・春・音楽祭」でたびたび共演しており、最近では2025年5月定期公演のマーラー《交響曲第3番》に出演している。今回の定期公演ではデュトワのタクトによる洗練されたメシアン、ホルスト作品の演奏に、華を添えてくれることだろう。
[伊藤制子/音楽学・音楽評論家]
DOWNLOADダウンロード
料金
| S席 | A席 | B席 | C席 | D席 | E席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 13,000円 | 11,000円 | 8,500円 | 7,000円 | 5,600円 | 3,500円 |
| ユースチケット | 6,500円 | 5,200円 | 4,000円 | 3,500円 | 2,000円 | 1,700円 |
※価格は税込です。
※定期会員の方は一般料金の10%割引となります。また、先行発売をご利用いただけます(取り扱いはWEBチケットN響・N響ガイドのみ)。
※車いす席についてはN響ガイドへお問い合わせください。
※N響ガイドでのお申し込みは、公演日の1営業日前までとなります。
※券種により1回券のご用意ができない場合があります。
※当日券販売についてはこちらをご覧ください。
※未就学児のご入場はお断りしています。
※開場前に屋内でお待ちいただくスペースはございません。ご了承ください。
ユースチケット
29歳以下の方へのお得なチケットです。
(要登録)
定期会員券
発売開始日
年間会員券/シーズン会員券(AUTUMN)
2025年7月13日(日)10:00am
[定期会員先行発売日: 2025年7月6日(日)10:00am]
BROADCAST放送予定
 NHK-FMベスト オブ クラシック
NHK-FMベスト オブ クラシック
「第2048回 定期公演 Aプログラム」
2025年11月27日(木) 7:35PM~ 9:15PM
曲目:
メシアン/神の現存の3つの小典礼*
ホルスト/組曲「惑星」作品32
指揮:シャルル・デュトワ
ピアノ:小菅 優*
オンド・マルトノ:大矢素子*
女声合唱:東京オペラシンガーズ
収録:2025年11月8日 NHKホール





