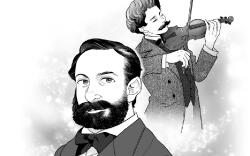- ホーム
- コンサート情報
- 定期公演 2024-2025シーズン
- Cプログラム
- 第2033回 定期公演 Cプログラム
※約2時間の公演となります(休憩20分あり)。
※やむを得ない理由で出演者や曲目等が変更となる場合や、公演が中止となる場合がございます。公演中止の場合をのぞき、チケット代金の払い戻しはいたしません。
ABOUT THIS CONCERT特徴
2025年2月Cプログラム 聴きどころ
粋なプログラムである。パリとウィーンで華開いたオペレッタの音楽の間に、フランスの作曲家サン・サーンスがスペイン人ヴァイオリニスト、サラサーテのために書いたヴァイオリン協奏曲が挟み込まれている。万国博覧会や芸術音楽の大衆化の時代。スター演奏家の存在と、笑いや技巧のなかに潜む芸術性。19世紀ヨーロッパの賑(にぎ)やかさには、足元が揺らぐ危うさもある。それを鋭く見抜いた作曲家たちの音楽もまた粋である。彼らに共通のエッセンスは、モーツァルトだ。
(安川智子)
PROGRAM曲目
スッペ/喜歌劇「軽騎兵」序曲
フランツ・フォン・スッペ(1819~1895)の名は、日本では浅草オペラや吹奏楽の分野でもお馴染(なじ)みである。現在はクロアチアに位置するオーストリア帝国ダルマチア(旧ヴェネツィア共和国領)の街スパラート(スプリト)に生まれたスッペは、1835年の父の死後ウィーンに渡り、本格的に作曲活動を開始した。同年生まれのジャック・オッフェンバック(1819~1880)がパリで音楽活動を開始する時期とほぼ並行している。
キャリアの初期にドニゼッティから助言を得て、1845年からは17年間、アン・デア・ウィーン劇場で楽長を務め、ここでマイヤベーアのグランド・オペラ《ユグノー教徒》やジングシュピール(ドイツ語の歌芝居)《シュレジェンの野営》などの指揮もした。オッフェンバックのパリ風オペレッタは、1856年にウィーンで初めて《2人の盲人》が上演されて以降大流行したが、スッペはそれ以前から、《詩人と農夫》など芝居用楽曲を数多く作曲していた。これらの経験が混ざり合い、スッペは「ウィンナ・オペレッタ」の創始者と目される作曲家へと成長していく。
《軽騎兵》はオッフェンバックの影響を受けたのちの1866年に、ウィーンのカール劇場で初演された2幕のオペレッタである。物語の主題は権力者の支配欲や結婚、親子であることの判明など、モーツァルトの《フィガロの結婚》によく似ている。現在もっぱら演奏される序曲は、物語に登場するハンガリーの軽騎兵の表象が中心となる。冒頭でトランペットからホルンへと受け渡されるファンファーレをはじめとして、軍楽隊風の勇ましさと爽快さが人気の理由のひとつだが、ふと挿入される哀愁的な旋律が、戯画化されたメロドラマのようで楽しい。
(安川智子)
演奏時間:約8分
作曲年代:1866年
初演:1866年3月21日、ウィーン、カール劇場
サン・サーンス/ヴァイオリン協奏曲 第3番 ロ短調 作品61
カミーユ・サン・サーンス(1835~1921)にとって協奏曲というジャンルは、尊敬する演奏家たちとの敬意に満ちた交流の場だった。19世紀のパリには、高度な技巧とショーマンシップを兼ね備えた名奏者たちが世界各国から集結した。サン・サーンス自身も、1846年にわずか10歳でピアニストとしてデビューした早熟の名鍵盤奏者であり、彼にとっての理想は常にモーツァルトだった。
スペインからやってきた名ヴァイオリン奏者パブロ・デ・サラサーテ(1844~1908)との出会いは、パリ音楽院での修学時代である。のちのサン・サーンスの追想によれば、ある日「春のように若くフレッシュな」サラサーテが協奏曲を書いてほしいと、彼のもとにやってきた。サン・サーンスは依頼に応じてヴァイオリン協奏曲の《第1番》を1859年に書き、その後1863年に《序奏とロンド・カプリチオーソ》を、そして1880年に本作《ヴァイオリン協奏曲第3番》をサラサーテのために作曲した。19世紀における演奏法の変化についても鋭い考察を行なったサン・サーンスは、サラサーテの演奏について、終始ヴィブラートをつけるような20世紀流の演奏ではなく、(《ヴァイオリン協奏曲第1番》の)両端楽章では情熱的に、緩徐楽章では湖のごとく穏やかに演奏することで大きな効果を生み出していたと、1915年の講演のなかで振り返っている。
第1楽章は、曲開始時にヴァイオリン独奏が奏でる4つ(+1つ)の断定的な音からなる主題が構造上の核となり、楽章全体に行き渡っている。第2楽章は変ロ長調に転じ、ヴァイオリン独奏が8分の6拍子で舟歌のように心地よく旋律を奏でる。第3楽章は妖艶な旋律と技巧性に富んだ、まさにサラサーテにふさわしい音楽で、愉悦を与えてくれる。冒頭から独奏が魅せる即興的な序奏主題のあと、ロ短調の民族舞踊的な第1主題、ニ長調の叙情的な第2主題、ト長調のコラール風主題と、4つのテーマが順に並置され、変化しながらも全体が再現部として繰り返される。再現部ではコラール風主題を金管楽器が軍楽風に色づけし、第2主題を利用したコーダでは祝祭的な雰囲気を伴って、賑(にぎ)やかに終結する。
(安川智子)
演奏時間:約30分
作曲年代:1880年
初演:1880年10月15日、ハンブルク、アドルフ・ゲオルク・ベーア指揮、フィルハーモニー管弦楽団、ヴァイオリン独奏パブロ・デ・サラサーテ
スッペ/喜歌劇「詩人と農夫」序曲
モーツァルトの《魔笛》公演で座長を務めたエマヌエル・シカネーダーが1801年に設立したウィーンのアン・デア・ウィーン劇場で、スッペは1845年から指揮者・楽長として働き始めた。劇音楽《詩人と農夫》が作曲・初演されたのはその翌年1846年である。この時はカール・エルマーの台本による喜劇の付随音楽だったが、1900年頃に、脚本家ゲオルク・クルーゼによって、スッペの音楽を用いた3幕のヴォードヴィル・オペレッタへと作り替えられている。物語は詩人と農夫をめぐる複数の男女の思慕が交錯するも、最後にはすべて解決するという、たわいないものだ。
本日演奏される序曲は、各場面音楽をつなぎあわせたメドレーのような作りとなっている。金管楽器の重奏につづいて、ハープの伴奏に乗ったチェロ独奏によるセレナーデ風の音楽で幕を開け、以後は疾走する爽快感とともに楽しめる。間に挿入されるワルツ風の楽句に、ウィンナ・オペレッタへとつながる特徴が垣間みえる。管楽器が活躍することから吹奏楽用にも編曲されて親しまれているが、とりわけ1961年に来日して以降日本の吹奏楽界に多大な影響を及ぼしてきたフランスの軍楽隊ギャルド・レピュブリケーヌ吹奏楽団が得意演目としており、彼らのベスト盤にも含まれている。
(安川智子)
演奏時間:約10分
作曲年代:1846年
初演:1846年8月24日、ウィーン、アン・デア・ウィーン劇場
オッフェンバック(ロザンタール編)/バレエ音楽「パリの喜び」(抜粋)
19世紀フランスの音楽劇は、パリの劇場文化と一体となって発展した。ドイツのケルン近郊に生まれたジャック・オッフェンバック(1819~1880)が、1833年に移住して活躍の場を見出したパリは、法によって劇場ごとにジャンルやレパートリーが細かく規定されていた。オッフェンバックは1855年のパリ万国博覧会を機会に、自作品を上演するブフ・パリジャン座を設営し、ここから快進撃が始まる。「オペレッタ」と呼ばれる、風刺の効いた筋と音楽、踊りを交えたジャンルは、オッフェンバックを通じて発展し、今日のミュージカルへと確実に受け継がれている。
1938年、オッフェンバックによる数々の名作をつなぎ合わせ、ひとつのバレエ音楽とすることを思いついたのは、バレエ・リュスで名を馳せた振付家・ダンサーのレオニード・マシーンである。ディアギレフ亡きあと、モナコのモンテカルロで活動を続けていたバレエ・リュスの演目として、エティエンヌ・ド・ボーモン伯爵が台本を担当し、編曲と管弦楽化を、まだ若きフランスの指揮者マニュエル・ロザンタール(1904~2003)が、オッフェンバックの孫の協力を得て実現した。
序曲と物語の大筋は、1866年に初演されたオッフェンバックの喜歌劇《パリの生活》から採用されている。1867年のパリ万国博覧会を記念して作られたこの作品は、外国人観光客が大挙して押し寄せ、拝金主義と欲望が蔓延する当時のパリの表と裏を、皮肉を込めて描いた傑作で、ロッシーニによる「シャンゼリゼのモーツァルト」というオッフェンバック評価を不動のものとした。バレエ版《パリの喜び》では、パリのカフェに次々と現れる個性的な人物を踊りと音楽で描いていく。
序曲のあとは、《地獄のオルフェ(天国と地獄)》のフレンチ・カンカン(第18曲)や、《ホフマン物語》の舟歌(第23曲)など、誰もが知るオッフェンバックの名曲を含む23曲で構成されるが、多くの場合抜粋で演奏される。ロザンタールによる、既存の楽曲から切り貼りしてつなぎ合わせる編曲法がすでに、無声映画の音楽作りで行われていた選編曲の手法にも似ているが、そこからさらにどのような構成で抜粋し、ひとつの管弦楽曲として聴かせるか、指揮者の選択の違いも楽しめる。
(安川智子)
演奏時間:約37分
作曲年代:ロザンタールによる編曲は1938年
初演:1938年4月5日、モンテカルロ(モナコ)、モンテカルロ歌劇場、バレエ・リュス・ド・モンテカルロ、エフレム・クルツ指揮
ARTISTS出演者
 指揮下野竜也
指揮下野竜也
下野竜也が私たちの視界に現れたのは2000年。第12回の東京国際音楽コンクール〈指揮〉(現東京国際指揮者コンクール)で第1位を得たときで、審査委員長はNHK交響楽団正指揮者の前任者のひとり、外山雄三だった。四半世紀近く経た2022年、下野は7年におよんだ広島交響楽団音楽総監督(現在は桂冠指揮者)6年目のシーズンに「次世代指揮者アカデミー&コンクール」を創設、「ひろしま国際指揮者コンクール」と改称した2024年は審査委員長をクリスティアン・アルミンクに委ね、自身は母体となる「ひろしま国際平和文化祭」の音楽プロデューサーに回った。同地では広島ウインドオーケストラ音楽監督も務め、NHK-FMの音楽番組『吹奏楽のひびき』ではアナウンサー顔負けの巧みな語りを披露する。コンクールや放送の分野でも、下野は外山雄三の衣鉢を継ぐ存在となりつつある。ウィーン留学で磨きをかけた和声感、フレーズ感を基本に音楽を豊かに歌わせる手腕は各地のオーケストラから評価され、独自のプログラミングでも注目される。N響2025年2月Cプログラムでもスプリト(クロアチア)に生まれウィーンへ移住したスッぺ、ケルンに生まれパリへ移住したオッフェンバックと、ともに1819年生まれのオペレッタ作曲家2人を対比させながら、サン・サーンスがヴィルトゥオーゾ(名手)サラサーテに献呈した《ヴァイオリン協奏曲第3番》(三浦文彰独奏)を添える華麗なメニューに臨む。
[池田卓夫/音楽ジャーナリスト]
 ヴァイオリン三浦文彰
ヴァイオリン三浦文彰
華やかな存在感を誇るヴァイオリニストで、2024年春にはブラームスのソナタ全集(ピアノ:清水和音)をリリースしたほか、イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団の定期公演に出演。NHK交響楽団の2025年2月の定期公演Cプログラムで弾く流麗なサン・サーンス《ヴァイオリン協奏曲第3番》への期待も、まさに限りない。
ウィーンでパヴェル・ヴェルニコフに師事し、2009年、16歳のときにドイツのハノーファー国際ヴァイオリン・コンクールで優勝。世界のトップステージに躍り出た。NHK音楽祭でグスターボ・ドゥダメル指揮ロサンゼルス・フィルハーモニックと共演しジョン・ウィリアムズ作品を奏でたほか、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団のアーティスト・イン・レジデンスに迎えられた。近年は指揮者としても活躍し、京都市交響楽団とのブラームス《交響曲第1番》が好評を博す。現在「サントリーホールARKクラシックス」のアーティスティック・リーダー。2024年6月には恩師徳永二男の後任として宮崎国際音楽祭の音楽監督に就任した。使用楽器は1732年製の銘器グァルネリ・デル・ジェス「カストン」。
[奥田佳道/音楽評論家]
DOWNLOADダウンロード
料金
| S席 | A席 | B席 | C席 | D席 | E席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 10,000円 | 8,500円 | 6,500円 | 5,400円 | 4,300円 | 2,200円 |
| ユースチケット | 5,000円 | 4,000円 | 3,100円 | 2,550円 | 1,500円 | 1,000円 |
※価格は税込です。
※定期会員の方は一般料金の10%割引となります。また、先行発売をご利用いただけます(取り扱いはWEBチケットN響・N響ガイドのみ)。
※車いす席についてはN響ガイドへお問い合わせください。
※N響ガイドでのお申し込みは、公演日の1営業日前までとなります。
※券種により1回券のご用意ができない場合があります。
※当日券販売についてはこちらをご覧ください。
※未就学児のご入場はお断りしています。
※開場前に屋内でお待ちいただくスペースはございません。ご了承ください。
ユースチケット
29歳以下の方へのお得なチケットです。
(要登録)
定期会員券
発売開始日
年間会員券
2024年7月15日(月・祝)10:00am
[定期会員先行発売日: 2024年7月7日(日)10:00am]
シーズン会員券(WINTER)
2024年10月15日(火)10:00am
[定期会員先行発売日: 2024年10月10日(木)10:00am]