ニュース
- ホーム
- NHK交響楽団からのニュース
- [SPOTLIGHT]インタビュー|ファビオ・ルイージ(指揮)に聞く ブルックナー《交響曲第2番》にみる輝きと美しさ(2022年12月Aプログラム)
[SPOTLIGHT]インタビュー|ファビオ・ルイージ(指揮)に聞く ブルックナー《交響曲第2番》にみる輝きと美しさ(2022年12月Aプログラム)
公演情報2022年11月 8日
2022年9月にN響首席指揮者に就任したファビオ・ルイージ。12月定期のA プログラムではブルックナー《交響曲第2番》を採り上げます。ブルックナーの初期作品を、また《第2番》の初稿を演奏するねらいはどこにあるのか、マエストロにうかがいました。
(聞き手・構成:広瀬 大介)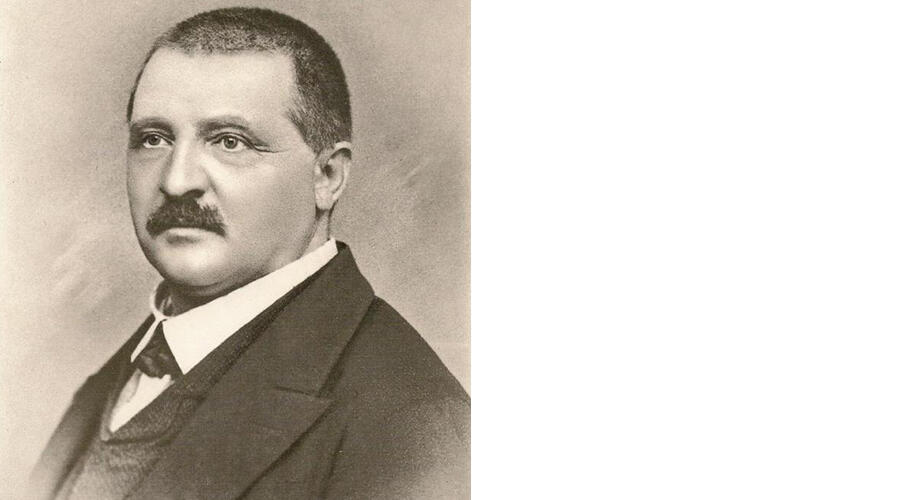
1868年のブルックナー
―ブルックナーに初めて出会われたのはいつだったのでしょう。ブルックナーをどのようにして学ばれたのですか?ルイージ: 出会い自体は若い頃、とても早い時期だったのですが、ブルックナー作品には、どうやって接していいのかわからないと感じていました。同僚の指揮者たちも、巨匠たちですら同じことを言うのです。ですが、オーストリアで研鑽(けんさん)を積んだ時期に学ぶことができたと思います。ブルックナーの人生を学んでいくことで、音楽というよりも、そのひととなりに近づけた気がします。
ブルックナーは、作曲家としては特殊な人生を歩んだと思います。ほかの作曲家と作風を比べられてしまうことへの葛藤もあったようです。田舎生まれで田園育ち、素朴な、とても宗教色が強い家庭で育ちました。厳格で古風なカトリックという環境で生まれ育った、そんな生い立ちを知ることから、ブルックナーに近づいてきた気がします。さまざまな要素が、ブルックナーの人格を形成していますよね。ものすごくシンプル、素朴でありながら、その一方で音楽への造詣は深い。シンプルさと複雑な音楽を知り尽くしている。この両極端な要素が同居しているところに、ブルックナーの理解を難しくしている理由があるように思われます。
ブルックナーはよく素朴だと言われますが、ただ単に素朴なのではなく、それは知識、教養に支えられたものでした。そのうえでシンプルな在り方を愛した。農民のようなところがありますが、すばらしく豊かな教養を湛(たた)えた農民であり、教師としてもたいへんに優秀なひとでした。そんなブルックナーの実像に、その巨大な世界観への入口に、何年もかけてやっとたどり着いたというところです。似ている作曲家を挙げるとすれば、やはりワーグナーでしょうか。ほかに類をみない作曲家だと思います。

― そんな独特なブルックナーの音楽にも、オーストリアならではの伝統を重んじているところはあるように思われます。
ルイージ: シューベルトととても近いですよね。両者の共通点を挙げるとしたら、自然にわきあがるような素朴さではないかと思います。シューベルトの偉大なピアノ・ソナタも、交響曲もそんな魅力を持ち合わせています。深遠な曲の中にも、ブルックナーに共通する点がありますね。ものごとの本質を衝(つ)くような、深みのある、そういったシンプルさに満ちた音楽、というべきでしょうか。
― 12月に採り上げる作品は《交響曲第2番》です。40歳代になってようやく交響曲を書きはじめ、そのスタイルが固まったのがこの曲なのでは、という印象があります。そこに至るまでの道程、たとえば3曲のミサ曲、あるいは《交響曲0番》などを経て成立した《第2番》という作品を、今回のプログラムに選んだ理由は、どのようなところにあるのでしょうか。
ルイージ: ブルックナーには、《第2番》に至るまで、後世に残っていない交響曲作曲の試みがもっとたくさんあったのでは、と思っています。現時点では《第0番》が知られていますけれども、ほかにもあったのではないでしょうか。交響曲を追いかけると、最後の《第9番》に至るまで、作曲家としての成熟の過程がつぶさに見て取れます。オーケストラの扱いにもだんだんと慣れてくる。《第8番》や《第9番》で完成をみるわけですが、《第7番》でもそのスタイルが垣間見える場所がありますよね。
《第2番》というのは、そのような、自己のスタイルを確立していく発展の途中にある作品です。作曲にあたっては、さまざまな試行錯誤を繰り返しています。苦労したのだろう、と感じられる形跡は、とくに第4楽章で顕著に見て取れます。同じような試行錯誤は《第0番》にもありますよね。この《第2番》になってようやく、成熟の萌芽が現れる。飛沫(しぶき)がほとばしるように、輝くような成熟が見えてくる。ブルックナー自身が、交響曲というものの価値を認めることができるようになってきたのでしょう。
その後、《第5番》《第6番》くらいまで待たないと、本当の成熟というのは見えてきません。《第3番》もとても好きですね。詩的で、誠実なシンプルさが見える。衒(てら)いのなさ、というべきでしょうか。大交響曲を書こうと思っているわけではなく、やはりシューベルト的な世界観の中にいる、というのが、その作品を美しくしている要因なのではないかと思います。

― 今回、初期の第1稿(1872年稿)を演奏することにされたのは、どのような理由があるのでしょうか。
ルイージ: 本当は全部の稿を順番に演奏したいのですが(笑)。稿や版の問題については、ブルックナーの思想、あるいはその変遷が見て取れます。ブルックナーは、仲間内の音楽家たちから、その影響をいとも簡単に受けてしまう(笑)。《第7番》第2楽章に書かれたシンバルを「無効gilt nicht」にするかどうかなど、稿の問題は多々ありますが、《第2番》の改訂には、さほど大きな問題点はないでしょう。
これだけ改訂を繰り返したのは、ほかの作曲家に対する劣等感の表れでもあったのではないでしょうか。それが、これだけの稿・版の錯綜(さくそう)を生んでしまっている。でも私は、その良し悪しの判断をしたくない。私たちができるのは、作曲家の作品を演奏して、それを差し出すこと。ありのままを見せることで、ブルックナーの思索がどのように変わっていったのか、それが重要だと思っています。
手紙などを読めば、ほかのひとに何を言われ、それによってどう変わったのかもわかります。その意味では、《第2番》はそこまで複雑ではありません。第1稿を選んだのは、これがブルックナー自身から自然に湧き出てきた形だと思うからです。もちろん後年の稿ではいくつか変更を加えていて、楽章配置など変更点もありますが、ブルックナーが模範とした、ベートーヴェン的な交響曲の理想形が現れています。
― N響との共演についての抱負を教えてください。
ルイージ:このコンサートが成功だったのかどうかに関しては、ぜひ演奏を聴いた方々に感想をうかがいたいと思っています。N響での演奏は、オーケストラの音楽的な表現力と私のアイデアがあいまって、とてもよい共振関係にあると思います。このコンサートでも、ぜひともよい演奏をお届けしたいです。
公演情報:
第1971回 定期公演 Aプログラム
2022年12月3日(土)開演 6:00pm
2022年12月4日(日)開演 2:00pm
NHKホール
ワーグナー/ウェーゼンドンクの5つの詩
ブルックナー/交響曲 第2番 ハ短調(初稿/1872年)
指揮:ファビオ・ルイージ
メゾ・ソプラノ:藤村実穂子

ファビオ・ルイージ(指揮)
1959年、イタリア・ジェノヴァ生まれ。デンマーク国立交響楽団首席指揮者、ダラス交響楽団音楽監督を務める。これまでにメトロポリタン歌劇場首席指揮者、チューリヒ歌劇場音楽総監督、ウィーン交響楽団首席指揮者、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団および同歌劇場音楽総監督、MDR(中部ドイツ放送)交響楽団芸術監督、スイス・ロマンド管弦楽団音楽監督などを歴任。このほか、イタリアのマルティナ・フランカで行われるヴァッレ・ディートリア音楽祭音楽監督も務めている。また、フィラデルフィア管弦楽団、クリーヴランド管弦楽団、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団、ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団、ロンドン交響楽団、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団、サイトウ・キネン・オーケストラに定期的に客演し、世界の主要オペラハウスにも登場している。録音には、ヴェルディ、ベッリーニ、シューマン、ベルリオーズ、ラフマニノフ、リムスキー・コルサコフ、マルタン、そしてオーストリア人作曲家フランツ・シュミットなどがある。また、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団とは数々のR.シュトラウスの交響詩を収録しているほか、ブルックナー《交響曲第9番》の解釈は高く評価されている。メトロポリタン歌劇場とのワーグナー《ジークフリート》《神々のたそがれ》の録音ではグラミー賞を受賞した。N響とは2001年に初共演。2022年9月、N響首席指揮者就任。
1959年、イタリア・ジェノヴァ生まれ。デンマーク国立交響楽団首席指揮者、ダラス交響楽団音楽監督を務める。これまでにメトロポリタン歌劇場首席指揮者、チューリヒ歌劇場音楽総監督、ウィーン交響楽団首席指揮者、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団および同歌劇場音楽総監督、MDR(中部ドイツ放送)交響楽団芸術監督、スイス・ロマンド管弦楽団音楽監督などを歴任。このほか、イタリアのマルティナ・フランカで行われるヴァッレ・ディートリア音楽祭音楽監督も務めている。また、フィラデルフィア管弦楽団、クリーヴランド管弦楽団、ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団、ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団、ロンドン交響楽団、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団、サイトウ・キネン・オーケストラに定期的に客演し、世界の主要オペラハウスにも登場している。録音には、ヴェルディ、ベッリーニ、シューマン、ベルリオーズ、ラフマニノフ、リムスキー・コルサコフ、マルタン、そしてオーストリア人作曲家フランツ・シュミットなどがある。また、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団とは数々のR.シュトラウスの交響詩を収録しているほか、ブルックナー《交響曲第9番》の解釈は高く評価されている。メトロポリタン歌劇場とのワーグナー《ジークフリート》《神々のたそがれ》の録音ではグラミー賞を受賞した。N響とは2001年に初共演。2022年9月、N響首席指揮者就任。
